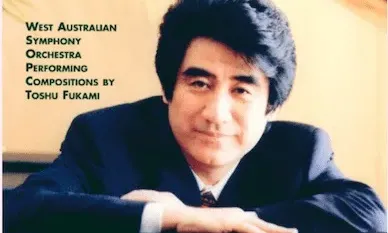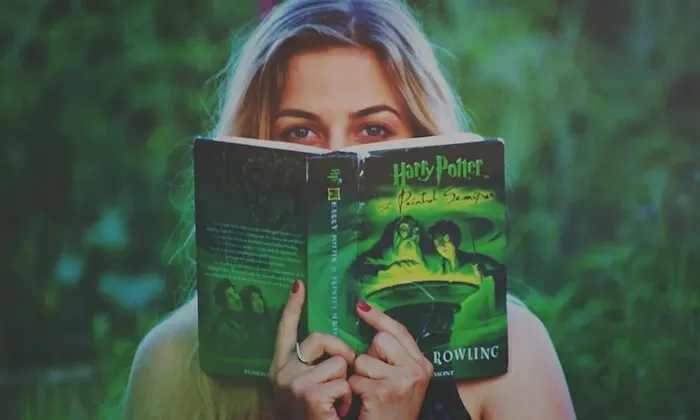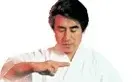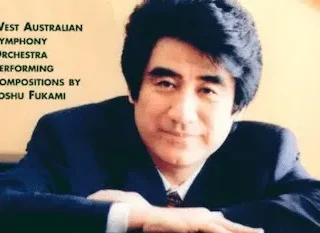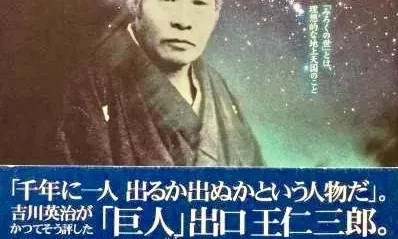
深見東州 (半田晴久) 氏の実業家としての詳細プロフィール

僕の個人的な見解ではありますが、世界の宗教グループや宗教家から優れた宗教家として評価されながら、なおかつ優れたビジネスマンとして、経営者として成功している人は、これまでなかなか現れなかったのではないかと思っています。
その両方に優れた才覚を発揮することは、とても困難なことなのかもしれません。
宗教への理解が浅い人の中には、宗教もビジネスみたいなものだろうと嘯く人もいます。
そのような人からすると、宗教とビジネスの両方やっていても不思議とは思わないかもしれませんが。
僕は昔から宗教をビジネスだと思ったことは一度もありません。
もしそのように感じる人がいるとするならば、それは単に宗教というものを知らないからだと思います。
宗教団体の組織運営ということに限るならば、施設の維持・管理の点で、企業と同じような原理や法則で動くこともあるでしょう。
そうしなければ、組織を安定して継続することが難しくなるからです。ただ、それを持ってして、宗教をビジネスと同じというには、無理があります。
宗教をやったことがある人、信仰を持っている人なら理解してもらえるかと思いますが、理屈抜きにビジネスとは全く違う感性の世界があると思います。
感性だけでは無く、心の持ちようや行いにも大きな違いがあります。
それだけに、全く違う能力が必要とされるビジネスと宗教を同時に行うのは、思っているほど簡単なことでは無いと、私は思っています。
そのことなども含め、深見東州先生のビジネスマンとしてのプロフィールの前に、宗教とビジネスの両方をなぜ行うのか。
また、なぜ両方とも優れたレベルで行えるのか。そのあたりのことから書いていこうと思います。
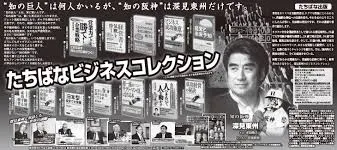
武田信玄型と上杉謙信型
先ほど深見東州先生は、世界の他宗教のグループや宗教家たちから、宗教家として高い評価を受け、かつ、優れたビジネスマンとしても成功していると書きました。
優れた経営者でありながら、信仰に篤い経営者や、あるいは宗教者としての一面も持つ経営者でしたら、日本では時々見かけます。
もしそれを戦国時代で言うならば、非常に優れた武将である武田信玄が、僧侶としての一面を持っていたことと似ています。
一方で戦国武将として、武田信玄のライバルとなる上杉謙信は、本来は僧侶として出家し、比叡山に行こうとしていました。
しかしそれでは上杉家が滅んでしまうからと家臣に懇願され、連れ戻されます。
戦国の世ですから、国を守るためには必ず敵を殺すことになる武将の道を選ぶことは、仏法の道を志した上杉謙信にとって、耐えられないことだったでしょう。
しかし上杉家と民を守るためには、現実に戦を避けることはできません。
そこで上杉謙信は、生涯妻帯しないと発願し、国を守る、義のためにしか戦わないと誓い、その代わり戦に勝ち民が守られますようにと、神仏に願っていたようです。
そのことをして、僧侶でありながら武将もやっていたのが上杉謙信だったと、深見東州先生は言われていました。

川中島の戦いで有名な「天と地と」を書いた海音寺潮五郎は、ウィキペディアにも書かれていますが、歴史の真実を伝えることに主眼を置く「武将列伝」で武田信玄を書くため、宿敵の上杉謙信のことも調べていました。
すると謙信の方がよほど純粋で魅力的であることに気がつき、のちに謙信を主人公に据えたこの小説を書くことになったそうです。
深見東州先生によると、上杉謙信には「敵に塩を送る」と言う精神に象徴されるように、領土欲のために戦をするのではなく、あくまで義のためにするものだと言う考えがあるそうです。
だからこそ神仏が守り、戦に勝つことができたのでしょうと、言われていました。
実は深見東州先生は、若いころから宗教家としてこれからの時代をどう生きていけば良いのか、常に自問自答していたそうです。
親鸞や法然、空海、最澄、そしてお釈迦様やキリスト、孔子や老子がこの自由経済で国際的な時代に生きていたなら、どうなさるのだろうかと、今でも自問自答されるそうです。
そして20代の時、米沢を訪れ、上杉謙信のお墓に参るため上杉神社を参拝した時に天啓を受けたそうです。
それ以来、上杉謙信のような生き方をしようと、同じ道を歩もうとされてきたそうです。
優れた経営者でありながら、信仰が篤く、宗教家としての一面も持つ人はかなりいると思います。
しかし優れた宗教リーダーでありながら、優れた経営者としての一面も持つ人は、なかなかいないのではないかと思います。
深見東州先生の経営者としてのあり方は、そのような上杉謙信型であり、武田信玄型ではないということが、まず大きな特徴のひとつになります。

実は僕はワールドメイトに入会するまでは、優れた経営者が信仰に篤いことは素晴らしいことでも、宗教家が経営者でもあると聞くと、どこかに抵抗を感じていただろうと思います。
しかし今では、それが宗教を知らない浅い考えであったことに気がつきました。
士農工商の江戸時代ならともかく、今ように経済活動が生活のメインと言える時代においては、宗教家であってもビジネスや経済のことを知らずして、人々を教化し救うことはできないのではないかと、思うようになりました。
今は武士の世、戦国時代ではありませんし、ファシズムや軍国主義の時代でもありません。
国家間における紛争や戦争はあるものの、昔のように、生き残りをかけて互いに殺しあうような時代ではなくなってきました。
しかし経済戦線と言われる、企業間においてはしのぎを削る自由経済の時代になっています。
そこで上杉謙信が仏法の道をもって戦にのぞみ、勝ち続け、国民を救ってきたように、深見東州先生も神人一体の道をもって、自ら企業家として経営に身を置くことにより、お金のありがたみを知り、経済の世に生きて苦しんでいる人たち、経営者の人たちの苦しみがわかって救っていけるのだと思います。
そして、上杉謙信が神仏に誓いを立てたのと引き換えに仏様の法力をいただいたように、深見東州先生も誓いを立て、神様から神通力とひらめきを受け、正しい教えを持って経済戦線や社会で苦しんでいる人たちを救い、国も守ろうという気持ちで会社経営をされているのだと思います。
聖と俗を区別して共存する日本の経営者
ここで、一つ注意しておかないといけないのは、上杉謙信型であろうが、武田信玄型であろうが、経営と信仰を両立させている人たちは、皆、信仰(宗教)と経営を区別した上で、共存させていることです。
ここも重要なポイントです。
出光興産の創業者は宗像大社を、西武グループの創業者は箱根神社の熱心な崇敬者として有名です。
松下幸之助は、根元の社という神社を作っていますが、辯天宗の宗祖から、これからの時代は電気だとアドバイスされ、その道に進んだそうです。
他にも、優れた事業家で、孤独や困難にぶつかった時に、仏教や神社の信仰によって超えてきた人は多いと思います。
見えない世界を扱う宗教と、現実社会そのものを扱う企業経営とは、一見すると矛盾するような取り合わせにも思えます。
まだ神道は、生業が栄えることを大事にしていますが、仏教になると、現世のことにはあまり価値をおいていません。
脱俗的な宗教であり、本来は出家思想と言えるものです。
にも関わらず、現実そのものを扱う経営者からの信仰が篤いのは、神仏習合などの歴史を経て、神道に基づく日本化された仏教だからだと深見東州先生は言われています。

その始まりは聖徳太子の選んだ三経義疏にあるそうです。
聖徳太子は出家主義の仏教に対し、在家というアンチテーゼになる「維摩教」と、仏教では不浄なものとして扱う女性を尊重する「勝鬘教」と、仏教が価値を認めない現実社会を理想郷にする「法華経」の3つを選びました。
それによって神道化が進んだということです。聖徳太子は、神道に適合する経典を選ぶことによって、仏教を日本に根付かせたようです。
また、日本古来の神道は皇室祭祀として残し、仏教は民衆の教化のために活用し、儒教は官僚や社会の道徳規範として用いたそうです。
そのように神道と仏教と儒教という違う宗教を、区別しながらうまく共存させることで、日本文化や社会を作ったそうです。
さらに政治には、宗教的なドグマを入れなかったそうです。
そのように、日本には区別して共存させるという神道の精神があります。
区別して共存させることで、現実の社会を繁栄させようというのが、今日まで日本の伝統になってきたそうです。
ですので宗教と経営、あるいは宗教家と事業家という、一見正反対で、同時に行えば矛盾をきたしそうなものでも、聖と俗を区別して共存することができます。
その結果繁栄し、現実の社会も良くすることができるわけです。
もしもこれが区別せずに、宗教と経営を混同してしまえば、どららも立ち行かなくなり、現実にも繁栄できなかったかもしまれせん。

ところで神道は外国からはアニミズムと思われているようですが、自然の全てに神がいるというわけではありません。
神います山や湖や海と、そうではない普通の山や湖や海を区別しています。
神山は大切にして守り、そうではない山は開発してきました。それによって、日本は繁栄できたのだと言われています。
その区別がなかったら、すべての自然を全く開発することができず、狭い国土で、現実的に繁栄できなかったでしょう。
また逆に、全てを開発してしまえば、神なる山も廃れてしまい、大変なことになります。
完全ではないにしても、神います自然と、そうではない普通の自然とを区別し、それぞれを使い分けることで共存させてきたからこそ、日本にとっては良かったのだと思います。
そのように、前述した経営者の方達も、皆、経営と信仰(宗教)を区別しながらも、共存させ、両立させてきました。
そこには何の矛盾もありませんし、それによって、現実もより良くすることができたのでしょう。
ちなみに海外では、聖である聖職者と、俗人である経済人は、明確に区別だけがされているようで、共存し両立させようという概念は無いようです。
敬虔なる神父さんが、バリバリの経営者として厳しい経済戦線も勝ち抜いている、という話は聞きませんからね。
宗教とビジネスを区別しないと、過度に宗教の教えを経営に導入することになり、ライバルに打ち勝つ気力もなくなって、結果会社は潰れて路頭に迷うことになるでしょう。
かといって宗教性を排除し、共存し両立させなければ、手段を選ばない、血も涙も無いような、自社の繁栄だけを考える企業になるかもしれません。
それではたして持続していけるのかは疑問です。
日本の企業は、海外に進出しても、その地域の人たちと共存共栄するようなやり方をするそうです。
対して欧米や中国の企業は、根こそぎ利益を持っていこうとします。撤退するときには何も残していかないとも言われます。
最近の欧米や日本企業のことはわかりませんが、そんな評判を昔は聞きました。
これも、神道の精神が根付く、日本人的な経営のやり方なのだろうと思っています。

話を深見東州先生のことに戻しますが、深見東州先生もワールドメイトを創設し、宗教活動を行う宗教リーダーですが、別に生業を持たれています。
現在、多くの会社を経営するビジネスマンであり事業家としても有名になられています。
しかしその経営に宗教活動を持ち込むことはされません。みすず学苑で宗教の話をしたり、勧誘することが全く無いというのはよく知られています。
あるとするなら、受験生が勉強ができるようになって希望する大学に入学でき、幸せな人生を送って欲しいという宗教的な情熱を学苑長が持っていて、それが熱心で面倒見の良い指導として現れていることくらいでしょう。
また、時計事業のハンダウォッチワールドでは、国内外に多くの取引先があると思いますが、その関係に宗教的な要素が入り込むことは全く皆無だそうです。
当然のことながら、ワールドメイトと、それらの株式会社との間にも、資本関係は無く、株も所有していないそうです。
聖である宗教と、俗であるビジネスをはっきりと区別した上で、上杉謙信のようなやり方で見事に共存させているのが、深見東州先生の宗教とビジネスの関係であり、両方を行う理由でもあり、結果現実を良くすることができる理由でもあると思います。
以上、僕の説明では、まだ誤解されやすい面や分かりづらい面もあったかとは思いますが、この自由経済と国際的な時代において宗教家としてあるべき道を、それが困難と誤解の多い道であったとしても、柔軟にたくましく歩まれていると思っています。
そして現代における上杉謙信型の経営者という誰も十分に成し遂げていない領域のことゆえ、神仏の守護も一層篤いのだろうと思います。
そこに深見東州先生の未知の可能性を感じてしまうところでもあります。
ビジネスマン、経営者としての深見東州先生の一面を理解するには、前提として、それらのことを知っておいた方が良いと思いましたので、最初に書いておくことにしました。
ビジネスマン、事業家としての歩み
深見東州先生は同志社大学を卒業後上京し、プレハブ住宅メーカー大手の大和ハウス工業に就職して、約1年ほど営業職につきます。
入社してすぐから目にとまり、当時の石橋社長の特命により一案件10億以上の工場や商業施設などを受注・建設する事業部に配属されます。
度胸と根性とピュアな気持ちがあるから建築をやらせてみようと、なったそうです。
そこで名物課長のもとで営業の基本を学び、すぐに頭角を現し、次々と新たな営業先を開拓することになります。
わずか1年の在職にはなりましたが、新入社員の中では、圧倒的なトップの成績だったそうです。
惜しまれながら1年ほどで退職すると、のちにワールドメイト開祖となられる植松愛子先生と、行動を共にされるようになります。
そして1978年26歳のときに起業し、受験のための学習塾(予備校)を西荻窪に設立します。

これが2024年現在、関東圏に12校舎を展開している「みすず学苑」になります。
現在は大学受験に特化していますが、ある時期までは高校受験クラスもあったそうです。
設立当時は、マスプロ教育の大手予備校全盛の時代で、そこに一人一人を丁寧に指導する個別指導を導入します。
後に増えていく、少人数制予備校の先駆けとなりました。
ユニークな電車広告やテレビ広告が毎年話題になりますが、難関大学への進学率が高いという指導実績を持つことでも評判です。

1979年には、健康器具や食品、文具、時計などを始め、様々な商品を扱う商事部を設立します。
時計事業に関しては、のちに流行するファッション時計の分野における先駆的な存在となります。
1980年からオリジナル時計の製造や輸入をスタートします。
また、国産のSEIKO(セイコー)、CITIZEN(シチズン)、CASIO(カシオ)も取り扱い、製造・卸・直販の会社として成長していきます。
1996年に、新宿高島屋の開業と同時に「時計の恋人」という時計ショップを出店します。
2011年にスイスの高級時計「カトレックス」の日本総代理店となり、2015年には「Roberto Cavalli by Franck Muller」の総代理店となります。
これが転機となり、ローエンド中心の卸・販売から、ミドルエンド、ハイエンド中心の卸・販売へと大きく業態が変化していきます。
それにともない、売り上げは黒字でしたが、高島屋の店舗をやめて、2017年から新たに「HANDA Watch World」という直営店舗を西荻窪に出店します。
その後も取扱う有名ブランドは増え続け、「カトレックス」や「Roberto Cavalli by Franck Muller」以外にも、「Hysek」や「JAERMANN & STÜBI」などの、複数の海外ブランドの輸入総代理店となります。

「HANDA Watch World」は2024年現在、全国主要都市に11店舗を展開しています。
それぞれの地域性を考え、異なるコンセプトを取り入れた店舗には、品揃えを含めて他にない特徴を持っています。
その時計事業部と、教育事業部、生活文化事業部の3つを擁するのが「株式会社ミスズ」で、1978年3月に設立されて以降、2010年代に100億企業となります。
それ以降現在も成長し続けています。
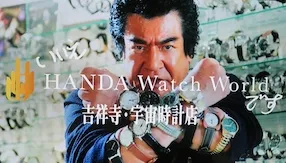
国内においては、1987年5月に出版業の、現「TTJたちばな出版」を立ち上げます。
深見東州先生自身の著作を始め、国内外の多くの著名な著者による書物を発行してきました。
深見東州先生の美術作品などを取り扱う「TOSHU絵描きの店」も、国内に3店舗展開しています。
「TTJ・たちばな出版」は斬新な販売キャンペーンや、ユニークな営業マンの存在でも話題になり、出版業界では異色の存在感を放っています。
1991年には、経営コンサルタント業務を行う会社も設立します。
こちらは現在は「株式会社菱法律・経済・政治研究所」という、会員数約5000名を擁する中小企業対象のコンサルタント会社として、各種セミナーなどを開催しています。
さらに、実践に即した経済や政治、法律を学んで、経営能力を磨くために、国内外の著名な政治家や経済学者、経営者、社会学者などを招いてシンポジウムを開催してきました。
主なゲストとしては、マーガレット・サッチャー元英国首相、ヘンリー・キッシンジャー元米国国務長官、ミハイル・ゴルバチョフ元ソビエト大統領、P.F.ドラッガー博士、サミュエル・ハンチントン教授、アルビン・トフラー、ダニエル・ベル、レスター・ブラウン、フリッチョフ・カプラ、フランシス・フクヤマ、ジョン・ネイズビット、ラビ・バトラなどなどの多彩な面々が来日し、講演や対談を行いました。

他にも国内においては、1982年設立の旅行会社、株式会社ジャパンペガサスツアー、1992年設立のヘルス&ビューティーに関する商品や医薬品を取り扱う、株式会社武蔵野メディカルを経営しています。
海外においては、37歳の時にオーストラリアで家具屋を買収したのを手始めに、その後、オーストラリアやイギリスにおいて、ヨットのマリーナ、ホビー牧場、ホテル、旅行会社などを経営します。
また、2017年に、経営が不安定になっていたゴルフに特化したスイスの高級機械式時計メーカー「JAERMANN & STÜBI(ヤーマン&ストゥービ)」からの救済依頼を受け、株式会社ミスズが買収し、深見東州先生がオーナー社長になり傘下に入ることになりました。

また、営利企業ではありませんが、国内外で多くの公益性を持つNPO法人や社団法人、財団を設立し、運営にあたっています。
それらの従業員を合わせると、おそらく600名は超えているものと思われます。
また、その1割ほどは欧米人などの海外の従業員になると思われます。
月刊誌に掲載された深見東州先生の営業力
ここからは、月刊誌「財界にいがた」が取材した「歌って踊るギャグ教祖、ワールドメイトリーダー深見東州の実像」という記事から、その一部を紹介します。
取材は深見東州先生へのロングインタビューという形で長時間にわたって行われ、「財界にいがた」の2018年11月号、12月号、2019年1月号に3回にわたり、長編掲載されました。(数値などはその時点のものになります)
深見東州先生の社会人なりたての頃のエピソードが、いくつか語られている部分のみ引用したました。営業マンとして、深見東州先生がどのような考え方、実践をしていたかを知ることができる内容です。
社長訓示を受けた新入社員が一人前に進み出て決意表明
——–深見先生は宗教家にかかわらず、プレハブ住宅大手として知られる大和ハウス工業の営業マンだったそうですね。
僕が大和ハウスに入社したての頃、社員集会の場に石橋信夫社長 (大和ハウス工業の創業者) が来られて、「オマエたち一人一人が社長になったつもりで行け!」と新入社員に喝を入れましてね。
それを聞いた僕の中に石橋社長の心が乗り移ってきて、「ワシが若いときのように、オマエたちは無から有を生むような強い気持ちで、なんでやらんのか !」という心の叫びを感じたのです。
僕は最前列に座っていたのですが、自分で自分のことを「ダメだ、ダメだ」と制止しているのにもかかわらず、もう神懸かっているものだから、体がフワリと自然に立ち上がってしまいましてね、社長の前まで歩いて行って、こう言ったのです。
「社長、おっしゃるとおりです。明日からは社長に成り代わって不可能を可能にする根性でいきますから !」
そうしたら社長以下、全取締役、全事業部長が呆気にとられて、みんなポカーンとしていましてね。 続けて僕が「明日から社長に成り代わってやりますから、社長の名刺をください !」と直訴したのです。
すると、やはりケミストリー (相性) ですね、石橋社長は「よし、分かっ た。石橋の名刺をやるからな。ええ根性や !」とおっしゃってくださいました。 そして石橋社長は僕にこう言ってくれたのです。「ええか、相手の弱点を掴むんや !」
それを聞いた僕は「ヨー シ、相手の弱点か・・・」と社長の言葉を胸に刻みました。その間ももちろん、居合わせた全取締役や社員たちはみんな呆気にとられポカーンとしているわけですよ。社員集会が終わった後、先輩からは「何をやっとるんだ !」とボロクソに怒鳴られましたけどね (苦笑)。
大和ハウス工業の創業者・石橋信夫氏は日本で初めて軽量鉄骨を使用したプレハブ住宅を製品化。住宅業界ではカリスマ的存在だったが、社員教育にも人一倍厳しかったと伝えられている。石橋氏の檄に触発され半田晴久 (深見東州氏の本名) 社員は早速、”魂の営業” に打って出る。
親戚に柴田護 (元自治省事務次官) という今日の地方自治行政の基礎をつくった人がおりまして、この方は昭和45年の京都府知事選に出馬し、蜷川虎三に敗れています。
僕の叔父さんに荻野益三郎という人がおりましてね、荻野さんのお嬢さんが柴田さんのもとに嫁いでいたのです。荻野益三郎は一高も東大も、司法試験も上級公務員試験も、全部首席で合格し、高裁の長官をやった人です。
本来は最高裁長官になれたのだけれど、争いごとが嫌いなのでライバルに長官の椅子を譲ったという高潔な方です。六法全書を一回見ただけで内容をすべて記憶したというほど頭が良く、「氷上郡が生んだ天才」とまでいわれた方でした。
柴田さんに嫁いだお嬢さんは一人娘だったのですが、荻野の叔父さんの奥さんは少しぼけていたのかもしれません、本音でぼやくわけですよ、「東京に嫁いだ娘がなかなか帰ってこないの・・・」と。
傍らの荻野の叔父さんは「柴田君も仕事が忙しいし、それに嫁いだ娘なんだから、そんなことを言うものじゃない」と奥さんを諭すのです。そう言いながらも、荻野の叔父さん本人も涙ぐんでるわけですよ。
その話を聞いて、僕は「一人娘なんだから、ときどき実家に帰らせてあげたらいいのに…」と、ずっと思ってたのです。それで、「これが柴田護の弱点だな !」と閃き、度胸試しにまったく面識もないのに柴田さんの自宅を夜訪したのです。
柴田護・元自治省事務次官からは「心理学を学べ」と
柴田さんの家の呼び鈴を鳴らすと「どなた様ですか ?」と尋ねられたので、「荻野益三郎の親戚の半田です」と言ったら、ご本人が「おお、どうぞ、 どうぞ…」といって家の中に通してくれました。
名刺を見た柴田さんが「建築の営業をしているということは、キミは営業に来ているんだね」と言うものですから、僕は「営業ですけど、今日来た理由は、僕の叔父さんのところに行くといつも “一人娘が柴田さんのところに嫁いで、何年も帰ってこない” と嘆く奥さんの傍らで、叔父さんが “それを言っちゃいけない。嫁いだ娘なんだから. …” といって涙ぐんでおられるので、せめて一年に一回は実家に帰らせてあげたらいいのではないかと言う、お願いに参ったのです」と申し上げました。
すると柴田護さんが 「ンッ・・・キミの言うとおりだ……」といって、奥さんを呼んでくれたんですね。 そこで僕はもう一度、「荻野の叔父さんのところに行くと、ご両親お二人とも毎回涙ぐんでいますよ。去年もいらっしゃらなかったでしょ ? 今日は一年に一回は帰ってあげてください、ということをお願いに参りました」と申し上げました。
これにはさすがの柴田さんも、「キミ、よく言いに来てくれた、ありがとう」といって涙ぐみましてね、ウィスキーを開けて下さり、歓談したのです。柴田さんは税務行政のトップも務めた方ですから、その経験を基にこんなアドバイスをいただきました。
「キミね、営業に行くときには2つのことを考えることだ。マルクスの『資本論』ではない、マルサスの『人口論』というものがあるが、業績が急に上がったり、急に下がったりしたとき、そういうときには必ずおかしな税務処理がなされていることが多いから、そういう企業に調査に入りなさいと、私は常々部下に指導しているんだ。それと同じでデータを追っかけていくことで営業の仕事は見つかるものだよ。だから、業界誌はよく見ておくべきだ。それと営業をするには心理学の勉強をしないとダメだ。 具体的には社会心理学だよ。これをもっと勉強すると営業マンとして立派になると思うよ」と。
そのアドバイスを聞い て、僕は改めて石橋社長の「相手の弱点を掴め !」という言葉を思い返し、根性試しも兼ねて次々とこの方法で営業をかけて行こうと決意したのでした。
社長訓示での直談判が 凄まじいインパクトを与えたのか、それまで特建と呼ばれるプレハブ工場や集合住宅の事業部に所属していた半田社員は、石橋社長の特命により、1案件10億円以上の工場や商業施設などを受注・ 建設する建築事業部に配属される。社長いわく「あの子には度胸と根性とピュアな気持ちがあるから、特建ではなく建築のほうをやらせてみよう」
当時、建築課には石橋社長の息子さんを立派に育て上げた、鶴田さんという名物課長がおりまして、僕は鶴田課長のもとに配属されたのです。そこでは、いろんな営業の基本を勉強させていただきました。
ある日、鶴田課長いわく「おい、半田、エスエス製薬が (福島県双葉郡)浪江町に総工費26億円の工場をつくるというんだが、営業マンが何度行っても門前払いなんだ。 オマエ、 行ってこいや !」というのです。
鶴田課長が重ねて「何をやってもいいから突破口を開いてこい !」というものですから、僕は「何をやってもいいですか ?」と念を押してエスエス製薬に行ってみました。すると話に聞いていたように、やはり門前払いです。「今頃になって来て、何ですか。お帰り下さい」 と言われたのです。「ああ、なるほど、これか…」と思いました。
“財界の怪物” エスエス製薬・ 泰道照山会長宅をアポなし夜訪
エスエス製薬に出向いて門前払いを食らった僕は一計を案じ、会社四季報を見ながら同社の組織図を書きましてね、 課長以上の人間の配置や序列を自分なりに整理していったのです。
当時、エスエス製薬の会長だった泰道照山は「財界の怪物」といわれていて、昭和30年代初頭に金融操作の誤りを原因に、経営危機に瀕していた同社をゼロから復活させた事実上の創業者です。 泰道照山の葬儀には田中角栄元総理も駆け付け、弔辞では創業者がいかに偉いかを力説していましたが、当時の田中派は竹下派による分裂という重大局面にありましたから、角さんは自分と泰道照山を重ね合わせていたのかもしれません。
さて、僕が独自につくったエスエス製薬の組織図を見ると、2億円の浪江町プロジェクトを受注するためには、どうしても「財界の怪物」といわれる泰道照山に直談判しなければならないという結論に至りました。そこで僕はまたしても度胸試しがてら、津田沼にある泰道照山の自宅をいきなり訪問することにしたのです。
夜8時半頃だったと記憶しています。「ピンポーン」と呼び鈴を鳴らすと、応対した家人が意外にも簡単に家の中に入れてくれて、お土産の葡萄を抱えて別室で待つことになりました。さすが「財界の怪物」だけあって、次から次へと客人が訪問してくるようです。
ほどなくして「オーイ、次の方を !」と声がして応接室に通されると、そこには泰道照山がいて「キミね、この人は三重県の北畠神社の宮司北畠さんなんだよ」と先客を紹介してくださるので、僕は「初めまして」と挨拶しました。 北畠さんが帰り、しばらくすると泰道照山もさすがに気付いたのか、「キミ、もしかしたら初めて会うんじゃないか ?」とおっしゃるので、「ええ、初めてお目にかかります」と。
「クボタハウスじゃないの?」 (泰道照山)
「いいえ、大和ハウスです」 (半田)
「クボタハウスかと思った。ところで何をしに来たんだ ?」 (泰道)
「いえ、それはもう、会長に是非お目にかかって、お聞きしたいことがあって来たんです」 (半田)
「ハァ ? なに ? キミ、 今日初めて会うんだよな ?」(泰道)
「初めてお目にかかります」 (半田)
「ワシは眠いから、早く用件を済ませてくれ」(泰道)
「分かりました。用件を簡潔に申し上げます。コレがエスエス製薬様の組織図です。トップが会長、こちらが遠藤専務、こちらが総務担当。そして御社には目下、浪江町に総工費26億円の工場を建設する計画がおありですね ?」 (半田)
「おう、あるよ」(泰道)
「ところがですね、御社にいくらうちの営業マンが出向いても “今頃来てもダメだよ” と言われるんですよ。オタクは工事業者を先着順で決めてるんですか ? 私ども大和ハウスは “技術が最高で、どこよりも工期が短く、どこよりも安い” のです。”技術が最高で、工期が最も短くて、値段が最も安い” という3大特色を持つ大和ハウスがあるのにですよ、先着順で工事業者を決めるなんてことはどうなのな・・・と思いまして」 (半田)
「いや、そんなことはない。今までの発注案件でも先着順で業者を決めたなんてことはない」(泰道)
「先着順ではないですよね」 (半田)
「そう、そう…」(泰道)
「じゃあ私どものように、 “技術が最高で、工期が短くて、値段が安い” ところがいいと思いませんか ?」 (半田)
泰道照山は「うん、そうだよね」と半分笑いながら聞いているわけですよ。そして泰道会長は「どうしてオレのところに来たのか ?」と尋ねるものですから、僕は「いったいどうしたら私どものような “技術が最高で、工期が最も短く、値段が最も安い” という3大特色を持つ会社が、御社から仕事をもらうことができるのか、会長にお聞きしたら分かると思って参ったのです。会長、どうしたら私どもの会社は26億円の工事をいただけますか ? それを教えていただきたいと思って今日は来ました」と言いました。
すると、泰道会長は一瞬押し黙った後に「ワッハッハッハッ・・・」と大笑いして、「いやー、キミは熱心だな。どこから来たんだ ?」と尋ねるので、「はい、北越谷です」と答えたら、「越谷から津田沼まで来たんかー。僕はキミのところの大和ハウスの石橋君のことをよく知っとるよ。こんな熱心な社員がいるとわなー」とゲラゲラ大笑いしましてね。
僕が重ねて「会長、教えてくださいよ」と頼んだところ、泰道会長は「先着順じゃないよ。取締役の村上君という総務部長に決定権があるから、彼のところに行かないと仕事はもらえないよ」と教えてくれたのです。
それで僕は「そうか、村上さんのところに行かなきゃ仕事をもらえないのか。分からなかったなぁー、さすが会長、会長に聞いてよかったです」と感謝の言葉を申し上げたところ、泰道会長は「キミは本当に熱心だねー」というものですから、僕は「なぜ熱心かというと、私どもの会社は “技術がどこよりも最高で、工期が最短で、値段が最も安い” ですから、こんな素晴らしい会社を使って仕事をしないのは、御社にとって損だと思って今日はこうしてお邪魔したのです」と。
エスエス製薬の取引先に竹中工務店や清水建設、大林組といったスーパーゼネコンがいるのは重々承知していたのですが、こうした超大手企業に立ち向かっていくためにはこの手しかなかったのです。
半田社員をネタにして業績アップを成し遂げた “財界の怪物”
加えて泰道会長にはこんなお願いもしました。「『財界の怪物」といわれる泰道照山会長の書は素晴らしいとお聞きしました。私に何か書いていただけないでしょうか ? 湊川の戦いに行くとき楠木正成公が “そもさんか、生死の境” と問うたのに対し、禅僧の明極楚俊は “両頭截断せば、一剣天によりて寒じ” (生死という分別の知恵の両頭を切り落とし、ただ黙々として雄々しく天の試練に立ち向かっていくことが、本当のわが生くべき真実の道なのだ) と答えていますが、私も今日はそういう気持ちで来たのです」
泰道会長は「ああ、あれ か・・・」と。僕が「色紙を持ってきたので書いてください」と頼むと、「よし、分かった。会社に小池君という秘書がいるから1週間後に取りに来なさい、書いておくから」とおっしゃってくださいました。その上で泰道会長は「いや、熱心やなぁー、面白いなぁー、まいったなぁー」といっては、野太い声で大笑いしていました。さらに泰道会長は「今度、石橋君に会ったら言っとくよ、”オタクの会社にはあんな熱心な社員がいていいなぁ” と」
1週間後にエスエス製薬さんにお邪魔したところ、小池さんが「会長から承っております」といって差し出したその色紙には「眉毛在眼上 (びもう、がんじょうにあり)」という、道元禅師の言葉が書かれていました。空手還郷、空手で行って空手で帰ってくるんだけれど、行く前も行った後も、ただただ当たり前に、眉毛は眼上に在りが分かっただけです。
「身心脱落、脱落身心」 と叫び、天童如浄の元で見性 (さとりを開くこと) した道元。当たり前のものを見る自分が、悟りを開いてもう当たり前ではない。この道元の言葉が、素晴らしい書で書かれていました。
今にして思えば、僕と会った第一印象が、眉が太くて長いので、眉の言葉にちなんだ前後にしたのでしょう。それともう一枚の色紙には、若山牧水の「白玉の歯にしみとほる秋の夜の酒はしづかに飲むべかりけり」という、有名な和歌が見事な万葉仮名で書いてありました。僕の持って行ったのとは違う色紙に書かれていましたから、何枚も書き潰して仕上げてくれたのだと思います。
僕が「素晴らしい書だなー」と感激していると、 小池さんは「会長はあなたのような人が好きみたいですよ」とおっしゃいました。僕は「そうかもしれないな」と思いました。創業者はゼロから会社をつくるわけですからね、泰道会長は全国の薬局を一軒一軒訪れ、あのエスエス製薬をゼロから育て上げた経営者です。
もちろん総務担当役員の村上さんのところにも行きましたが、村上さん はその後、何度出向いても僕の顔を見るたびに「あっ !」といって逃げるんです。まったく話などできません。
とはいえ、もともと度胸試しの営業でしたから、これでよしとしました。僕にしてみれば「まいったか、度胸では負けないぞ、この財界の怪物め !」といったところです。
後に人づてに聞いた話ですが、泰道会長は僕がいきなり夜訪した翌日の朝礼で、社員に向かってこう檄を飛ばしたそうです。「昨夜9時頃、自宅におったら大和ハウスの半田という営業マンが “オタクの浪江町の26億円の工事をどうしたらもらえるか、会長に聞きに来ました” といって、堂々とやって来たんだ。 エスエス製薬にはあんな熱心な社員はいない。これは、ひとえにうちの会社の努力目標が低いためだから、今後はノルマを15%引き上げる !」と。 その結果、社員たちは15%アップのノルマを見事に達成したといいます。
さすがは泰道照山だなと思いました。いきなり会長に営業をかけたのは僕ですが、その話を、朝礼で持ち出し会社の業績アップ につなげてしまうんですからね。その後、泰道会長は朝礼で社員らを前に、マイクで「オレはがんだから、来月もう死ぬわ」 といって、その言葉どおりこの世を去ったといいます。物凄い野太い声の坊さんのような人でした。
「これこそが財界の怪物 か・・・」と思いましたが、僕自身も「もう会社なんてクビになってもいいわい !」 という決意で、真正面から飛び込んでね、「ブチ殺されても行ってやるわ !」という根性ですな、そういうケミストリーをお互い感じたのだと思います。
休業日の会社に “侵入” して名刺1000枚で無言のご挨拶
“営業の半田、エスエス製薬会長の自宅をいきなり夜訪” のニュースは、当然ながら大和ハウスの社内を瞬く間に駆け巡る。
この話を聞いた早矢仕建築事業部長が鶴田課長に指示したのだと思いますが、課長が「半田、印刷機器会社のコピアだが、営業マンが何度行っても門前払いなんだ。半田よ、何をやってもいいから突破口を開いてこい !」というのです。「何をやってもいいんです か ?」 (半田)
「何をやってもいい」(鶴田課長)
「本当に何をやってもいいんですか ?」 (半田)
「本当に、何をやってもいい !」 (鶴田課長) と、こうまで言われたものですから、僕も「分かりました」といって引き受けました。
そしていざコピアを訪問してみると、やはり門前払いでした。そこで、まずは名前を覚えていただかなければいけないということで、〈大和ハウス工業 建築営業 半田晴久〉の名刺を1000枚刷りました。そして土曜日、つまり会社が休みの日にコピア本社に出向いて守衛さんに 「どうも、どうも、カギを忘れまして・・・」と適当なことを言ってカギを借りて社内に入ったのです。
それで「ここが社長室だ ・・・」ということで、机の正面上に名刺を10枚、「ここが専務の机だな・・・」ということで名刺を8枚、常務の席に6枚、部長の席に5枚、課長に3枚、平社員、事務員の席にも1枚ずつ名刺を置いて、要は1000枚の名刺を、すべて置いてきたのです。
すると、明けて月曜日のお昼ごろに早矢仕建築事業部長が「おい、半田、ちょっと来い」といって僕を呼んで、「オマエ、コピアという会社を知っとるか ?」というので、「ああ、知ってますよ」と。
「ひとつ質問やけど、世の中に軽犯罪法というのがあるのを知っとるか ?」(建築事業部長)
「よく存じております」(半田)
「それならいいんや。実はコピアの総務部長さんから電話がかかってきて、”今朝出社したら社員がみんなワイワイ大騒ぎしていて、社長が『ワシの机の上に大和ハウスの半田という営業マンの名刺が10枚ある』と言ったかと思えば、専務も『私のところにも8枚あります』といった具合に、社内が「なんだコレは !」と大変な騒ぎになっている” ということなんだ。総務部長は役職別にちょっとずつ名刺の枚数に差をつける “手口” も不可解極まりないと首を傾げていたが、それにも増して何か盗まれたものがないかどうか確認したが、何も盗られたものはない。それで、守衛も呼んで、セキュリティーを再チェックしたらしい。それにしても半田、いったいどうやってコピアの社内に入ったんだ ?」(建築事業部長)
僕は、たしかに守衛さんからカギを借りて社内に入りましたが、もちろん何も盗んではいません。時間経過とともにコピアの関係者もそれが分かってきて、「どうやら半田という営業マンは、営業のアピールのためにやって来たのではないか ?」「もしそうだとすれば物凄い営業マンで、我が社にはここまでする熱心な営業マンはいないよな」といった話になったらしいのです。
その上で、コピアの総務部長が「おたくに半田さんという営業マンは実在しますか ?」と尋ねると、早矢仕事業部長は「はい、おります。新入社員ですが、頑張っております」。
すると、総務部長はこう話したというんですね。「もしも、彼が営業のために名刺を配ったのだとすれば、是非とも咎めないでやってください、叱らないでやってください。これは社長以下、うちの会社の役員、社員の総意なのですが、コピアは印刷機器業界の中で生きるか死ぬかの競争をしているのに、これくらいの度胸と根性と熱心さがないと、うちの会社は生き残れません。だから、この半田君のような営業姿勢を見習わなければなりません。ですから、是非とも半田君を叱らないでやってください、彼は御社にとっても大事な人材のはずです。社長以下、この半田君はどんな人物なのか、みんな会いたがっています。一 度、彼を我が社に連れて来てくれませんか。私も会いたいです」と。
事業部長が僕に「オマエが軽犯罪法を知っとって、そういうことをやったのならそれでいい」というものですから、僕は「鶴田課長が “半田、何をやってもいいから、突破口を開いて こい ! ” とおっしゃったから、軽犯罪法スレスレのところで名前を覚えてもらうためにやったのです」と返しました。
すると、傍らにいた鶴田課長が「よくやった、半田。 コピアに一緒に謝罪しに行くときには、オマエはうつむき加減でシューンとしてるんだぞ、その隣でオレがしっかりと営業するから」といって後日、実際に先方に出向きました。
鶴田課長が総務部長に「うちの半田も新入社員でして、一生懸命に営業をしようと考えたんでしょうが、つい行き過ぎたことをいたしまして誠にすみませんでした」と謝る傍らで、僕は下を向いてショボーンと小さな声で「はいー」といって “反省しきりの新入社員” になっていました。
するとコピアの社長や専務、常務、部長らが「おお、キミが半田君かぁ…」と、何か珍しいものでも見るような、嬉しそうな顔で僕のところに次々とやって来るのです。その都度、僕は「初めまして・・・」と挨 拶しましたよ。
そして鶴田課長がひとしきり謝罪を終え、「ところで会社四季報を拝見しますと、御社は相当な利益を出しておられるので、工場や社員寮などをおつくりになる際には、是非とも弊社にも相見積もりを出させてください」と切り出すと、総務部長は「是非お願いします。すでに、社員寮を作る計画がありますので、是非相見積もりに加わって下さい。われわれ印刷機器メーカーも半田君くらい熱心に営業をやらなきゃいけません、見事なものですよ。 彼を大事にしてやってくださいね」と おっしゃってくれました。
帰りの道中、あの恐い鶴田課長から「半田、よくやったな」と言ってもらいました。営業は突破口を切り開くまでが大変なのです。その後も、僕は夜討ち朝駆けの、千変万化の営業戦術を展開し、成田ビューホテルの建設の相見積もりにも参加させていただくなど、次々と新たな営業先の開拓に成功しました。新入社員の中では、圧倒的に成績ナンバーワンだったのです。
スケールの大きな建築の営業が、僕には合っていたのでしょうね。石橋社長の目に狂いはなかったのです。だから、事業部長ももはや心得たものです。「半田、オマエな、今度は東芝に行かんか ? 東芝への営業も行き詰まってるんや」と言ったかと思ったら、「半田、次は日立を頼むわ」といった具合でしたからね (笑)。