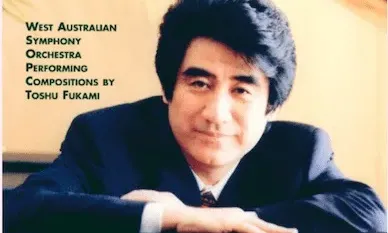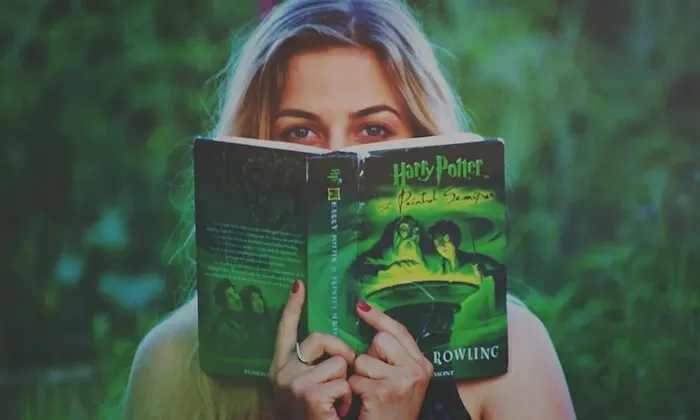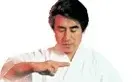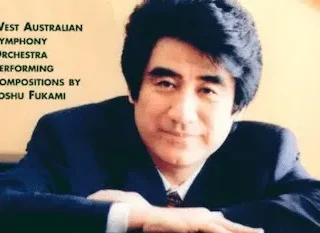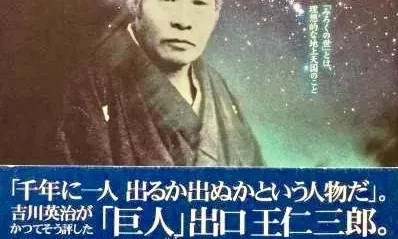
ワールドメイトで先祖供養の意味を知り、家運が変わる

今年も夏は記録的な酷暑が続いています。少し前までは、8月15日のお盆が過ぎると暑さが和らいでいましたが、ここ数年、それも期待できない環境になってきました。
日本人がお盆に先祖供養する理由は
ところで昔のお盆というのは、旧暦の7月15日だったそうです。明治になって新暦を採用した時に、そのまま旧暦の7月15日に行うところ、新暦の7月15日に行うところ、農家が忙しいので一ヶ月遅い8月15日にしたところ、いろいろ別れてしまったようですね。
僕が所属するワールドメイトの支部に、沖縄が地元のワールドメイト会員がいたのですが、いつも8月の終わり頃(旧暦7月15日)に沖縄に帰省していました。西日本、東北、北海道が地元の人たちは、8月12日頃に帰省します。昔から関東に住むワールドメイト会員は、7月15日にお盆を済ませる人が多いですね。
首都圏には全国から人が集まっていますが、地方に帰省する人の多くは8月13日ごろか、それより前になりますので、仕事の「お盆休み」と言うと、全国的には8月の13~15日を含む週となっていますね。そのため「お盆」と言うと8月15日というのが一般的になったようです。

お盆には「送り火、迎え火」「灯籠流し」などもがあり、さらに初盆では特に手厚く故人を供養したりします。なぜ先祖供養をするかというのも、いくつかの説があるようです。
有力な説は、もともと日本にあった先祖崇拝の習慣が、仏教の盂蘭盆会と習合して、お盆の先祖供養という形になったというものです。古来神道では、先祖を遡ると神様にたどりつくと言われています。古事記などを見ても、そのことは明らかです。だから先祖崇拝は神道に昔からあったのでしょう。
また、初春と初秋のある時期には、祖霊が子孫と交流するために帰ってくると言われていて、それが正月(節分)行事、お盆の頃の行事になっていったのでしょう。
ワールドメイトで聞いた話では、昔は正月が2度あり、年越の大祓と夏越の大祓のあとに正月を迎えたそうです。この2度の正月が、仏教伝来後に今のような神道式の正月と、盂蘭盆会と結びついたお盆になったとのことでした。
Embed from Getty Imagesちなみに仏教そのものには先祖崇拝の教えは無く、中国でできたと言われる盂蘭盆経に、次のような説話が残っているのみでした。
『安居の最中、神通第一の目連尊者が亡くなった母親の姿を探すと、餓鬼道に堕ちているのを見つけた。喉を枯らし飢えていたので、水や食べ物を差し出したが、ことごとく口に入る直前に炎となって、母親の口には入らなかった。哀れに思って釈尊に実情を話して方法を問うと、「安居の最後の日にすべての比丘に食べ物を施せば、母親にもその施しの一端が口に入るだろう」と答えた。その通りに実行して、比丘のすべてに布施を行い、比丘たちは飲んだり食べたり踊ったり大喜びをした。すると、その喜びが餓鬼道に堕ちている者たちにも伝わり、母親の口にも入った』
この伝説からきた盂蘭盆会が、救われていない先祖を供養するためのものであったようです。日本古来の先祖崇拝は、もう少し明るいイメージですが、盂蘭盆会はやや暗いイメージですけどね。それでも、両方ともに霊界の真実の一端をとらえているようです。それらが神仏習合して現在のようなお盆の先祖供養へつながっていったのでしょう。
ワールドメイトは神道ですが、お盆の時期には先祖供養を行います。このような深い意味があるからこそ、ワールドメイトでも行われているわけですね。

ワールドメイトに入会し、初めてお盆の意味を考える
僕の小さい頃のお盆の思い出になりますが、祖父祖母の家に親戚が大勢集まり、仏壇の前にはきれいな灯籠がたくさん並べられ、美味しいものをいろいろ食べながら、従兄弟たちと遊んでいた記憶があります。かなり毎年盛大にやってました。
もちろん送り火、迎え火もありましたし、初盆がある時は、灯籠流し(精霊流し)で、先祖が住んでいた地域の海に流しに行っていました。またお坊さんも来て、お経を唱えていました。
よく意味もわからないまま、とにかくお盆には曾おじいちゃんや曾おばあちゃんも帰ってきてるからね、といわれました。家の先祖が帰ってくると言うことだけは、かろうじて理解できました。そして先祖伝来の土地にあるお墓参りにも、毎年行っていましたね。

今思うとお盆の過ごし方としては、まあまあ、よかったのかもしれません。しかしいつの頃からか、お盆のそういう伝統も途絶えぎみになっていき、簡単に済ますようになってしまいました。
ワールドメイトに入会したのは、ちょうどそんな頃でした。そこで僕は生まれて初めて、先祖供養について真剣に考えました。といっても、そんなに大げさなものではなく、年に2回ほど、節分とお盆の時期に考えるだけでした。それ以外のときは神仏に心を向けても、先祖や霊界に心を向けることはほとんどありませんでした。
年に2回、節分(旧正月)とお盆の頃に、日本では霊界の先祖との交流が昔からあったそうです。その頃に先祖が帰ってくるから、その前に、年越の大祓、夏越の大祓いを行ってたまった穢れを清めて正月を迎える、という慣習があったようなのです。ちなみにユダヤ人にも、似たようなことをするならわしがあるそうですが。

そういうDNAが日本人の中に流れていることを理解すると、思い当たることがあります。お盆の供養を盛大にしていた頃に比べて、だんだんしなくなるに従い、まるで呼応するかのごとく家系の運気が下がっていったことです。
それは親戚一同も含めてなのですが、〇〇家一族の威勢がなぜか衰退している感じを受けました。それは、時代の流れなのだろうで済ませていましたが。
それから僕の体にだんだん変調が現れてきたことがあります。たとえば軽い喘息にかかったことがありました。それ以外にも原因不明の病にかかることがあったりしました。親にも随分心配をかけていたようです。
さすがに社会人になるころには、からだの変調もなくなり、元気に頑張るようになりました。しいていえば、節分とお盆の時期になると高熱を出し、寝込むとかはありました。
それらが、すべて先祖供養をしなくなったからだとは思いませんが、今思い返すと、やはり先祖の影響も大きかったのだったのだろうと感じます。
僕の実感としては、ワールドメイトに入会し、先祖の影響の実態を知って、正しい先祖供養を行うようになったことで、家の衰運に歯止めをかけることができたと思っています。
その前にまず個人の運勢が随分よくなりましたけどね。家全体となると、そう簡単に変わるものではないと思いますが、それでも身近なところから少しづつ変わっていきました。
家の事業や、結婚や子どものことなど、家系の衰運や盛運と大きく関係していますが、先祖の影響が良きにつけ、悪しきにつけあるわけですね。

もちろん、先祖供養のために人生があるのではありませんから、年中気にして、あまりやりすぎるとよくないのも事実です。供養ばかり気にかける人生は、霊界に波長が合いすぎて、かえって逆効果になることだってあります。
人生の本質とは、もっと他のところにありますからね。ワールドメイトでよく言われるのは、自分自身を立派に磨いていくことが、なにより大事なことだと知りました。
本当は、それだけでもいいくらいですが、でも現実のお金や健康、仕事や結婚や人間関係などに、かなり強く影響を与えているのも先祖です。お盆の許された時期に、感謝の心をもって供養を行えば、現実の生活にプラスになるのも間違いなく事実だと言えます。